
2004/04/01
21世紀COE「太陽・地球・生命圏相互作用系の変動学」 2003年度報告書の一部(安成先生執筆)を掲載します。
序章 「太陽・地球・生命圏相互作用系の変動学」とは
安成哲三
地球水循環研究センター
1 はじめに
平成15年度「21世紀COEプログラム」の数学・物理学・地球科学分野に、本学の地球科学関連4組織(環境学研究科地球環境科学専攻、太陽地球環境研究所、地球水循環研究センター、年代測定総合研究センター)から提案した「太陽・地球・生命圏相互作用系の変動学」が採択された。このCOEは何をめざしているのか。拠点リーダーとしての考えを以下に簡単にのべたい。
20世紀の地球科学は、地球を細分化し、それぞれの現象・プロセスに近代物理学・化学の手法と考え方を導入して解明を進めてきた学問分野といえる。そして、それぞれの分野において、新たな現象の発見、解明を含めて、近代的な地球科学諸分野が発展し、それぞれの分野に対応した多くの学会が設立されている。この流れはもちろん、否定すべきものではなく、科学の歴史的発展の一段階として必然の帰結であるともいえる。
良くも悪くも「グローバル」に拡大・発展してきた人類活動は、一方で、地球温暖化やオゾンホールに代表されるいわゆる「地球環境問題」を引き起こしている。しかし同時に、この人類の知的活動の進展により、地球が、太陽エネルギーを受けながら、さまざまな物理・化学プロセスが相互に密接に関連して機能し、進化してきたひとつのシステムであることを再認識させることにもなった。そして、人類を含めた生命圏も、このシステムの進化・変化の過程に能動的に働きかけながら、現在の地球をかたちづくってきたことが、すこしづつ明らかになってきた。
たとえば、大気のオゾン層は、太陽からの紫外線フィルターとして、生命圏の維持に不可欠な役割を果たしていることがわかっているが、このオゾン層は対流圏からの酸素の絶えざる供給によって維持され、その酸素はもちろん、生命圏の光合成活動により維持されている(図1)。オゾン層のもうひとつの重要な機能は、大気成層圏の維持であり、比較的低い高度に維持されている成層圏の存在が、コールド・トラップとして機能して生命にとって不可欠の水物質の保存と水循環を含めた、地球表層と対流圏における閉じた物質循環を保障している。すなわち、オゾン層と生命圏は、相互にその維持を担う共生系を成しつつ形成されてきたことがわかる(安成, 1999;岩坂・安成, 1999)。
一方で、強烈な太陽風エネルギーから生命圏を保護してきたのは、地球磁場の存在である。地球磁場の維持と変化によるオーロラの変動や、その変化機構を担う固体地球内部のダイナミクスも、地球表層の生命圏の進化と決して無縁ではないことがわかる。地球磁場は数万年から100万年のスケール(周期)で反転を繰り返しており、生命圏の進化に、時として大きなインパクトを与えた可能性が指摘されている。太陽活動そのものの変化に加え、地磁気変化を通した地球表層圏への太陽エネルギー配分過程の変化は、生命の進化と地球環境変化の外部条件として、見逃すことができない重要なプロセスである(図2)。
現在の地球の生態系も、水・物質循環を介し、気候と共生的関係にあることが、ここ1996年以来、私を代表として進めてきたGAME(アジアモンスーンエネルギー・水循環研究観測計画)などの観測的研究で明らかになってきた。ユーラシア大陸高緯度のシベリアには、永久凍土帯が広がり、その凍土の表層はタイガ(針葉樹林帯)に覆われている。永久凍土は夏季にのみ表層わずか数十センチだけ融解するが、その浅い融解層にたまった水を、タイガは浅く横に広く広がった根っこで効率よく吸収し、光合成と蒸発散を同時に行って、自らを維持している。いっぽう凍土帯は、タイガの被覆と蒸発散による表面温度上昇の抑制により、夏季の融解を最小限に抑え、自らを維持している。すなわち、永久凍土とタイガは水・エネルギー循環を通して、お互いに維持しあった一種の共生系をかたちづくっているともいえよう(Ohta et al., 2001)。アマゾンや東南アジアの熱帯雨林も、水循環とエネルギーの流れの強さは、シベリアのような寒帯とは大きく異なるが、やなり同様の気候と植生(生態系)の共生系として維持されていることが近年の観測的研究から明らかになりつつある(図3)。このような共生系は、いったん一部でも破壊されれば、急激に変化してしまう特性を持っている可能性は想像に難くないであろう。
このような地球システム全体を、太陽・地球・生命圏相互作用系と捉え、過去から現在に至るこの系の変化のダイナミクスを改めて理解することは、物理学・化学の応用問題としての地球科学ではなく、地球という惑星そのものが何であるかを考究する新たな「地球学」の構築をもめざすことにもなる。そして、この地球学は、人類を含む生命圏の存続と発展(進化)が、今後どのようなかたちで有りうるか、起こりうるかを考える基礎と契機になりうるはずである。
このCOEプログラムでは、特に第三紀から現在を含む第四紀にいたる過去約1000万年の地球環境変化に着目する。その理由のひとつは、湖底、海洋底堆積物、氷床コア、年輪などにもとづく高精度の環境変動復元と、過去数十年程度の全球的な観測データにもとづく現在の地球システムのプロセスとを、密接に関連させることにより、現在の地球環境の理解にも直接的につながる地球変化のしくみの解明がめざすことにある。この時期は、 図4に示すように、氷河時代を含めて、全球的に寒冷化が進行しており、そのようなトレンドの中で、人類が出現し、地球環境の変化に関わってきた。このような時期の環境変化の解明は、近年の「地球温暖化」を引き起こしているとされる人類と地球の関わりを、より深く理解するためにも、非常に重要なことである。
さいわい、名古屋大学には、すでに1960年代から世界に先駆けて、地球をシームレスな(縫い目のない)システムとして理解しようとした島津康男、生命圏を含む全地球史を解読しようとした熊沢峰夫らの、地球をシステムとして、あるいは丸ごと理解しようとする伝統が地球科学科と環境学研究科に今も息づいている。一方で、地球表層を、大もとのエネルギーである太陽活動の変動から高層大気の変動、電磁気圏変動と太陽エネルギーとの相互作用などの研究を進めてきた太陽地球環境研究所、大気・水圏での水と物質の循環と気候の研究を進めてきた大気水圏科学研究所(現在は地球水循環研究センターと環境学研究科)での研究の蓄積も行われてきた。日本でもユニークな年代測定総合研究センターは、高精度の時間分解能を誇るタンデム型質量分析計を中心とした環境変動解析の実績を積んでいる。「相互作用系の変動学」は、このような実績を持つ本学の地球科学分野が連携・協力して進める新たな研究の流れとして、必然的に生まれてきた概念である。
参考文献
岩坂泰信・安成哲三(1999):地球システムの進化と大気環境の変化. 岩波講座地球環境学3 大気環境の変化(安成哲三・岩坂泰信編),第1章, 1-48.
Ohta, T., Hiyama, T., Tanaka, H., Kuwada, T., Maximov, T.C., Ohata, T. and Fukushima, Y., 2001: Seasonal variation in the energy and water exchanges above and below a larch forest in eastern Siberia, Hydrological Processes, 15(8), 1,459-1,476.
安成哲三(1999):地球の水循環と気候システム. 岩波講座地球環境学4 水・物質循環系の変化(和田英太郎・安成哲三編)」、第1章、1-34.
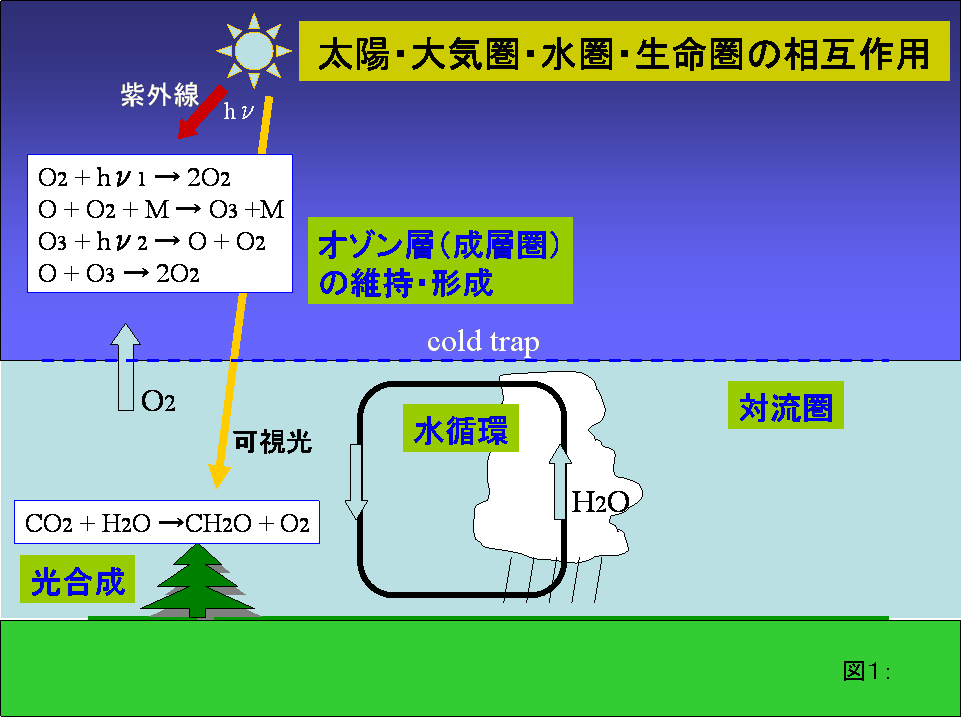
図1:オゾン層(成層圏)と生命圏の光合成活動および水循環の相互維持機構の模式図
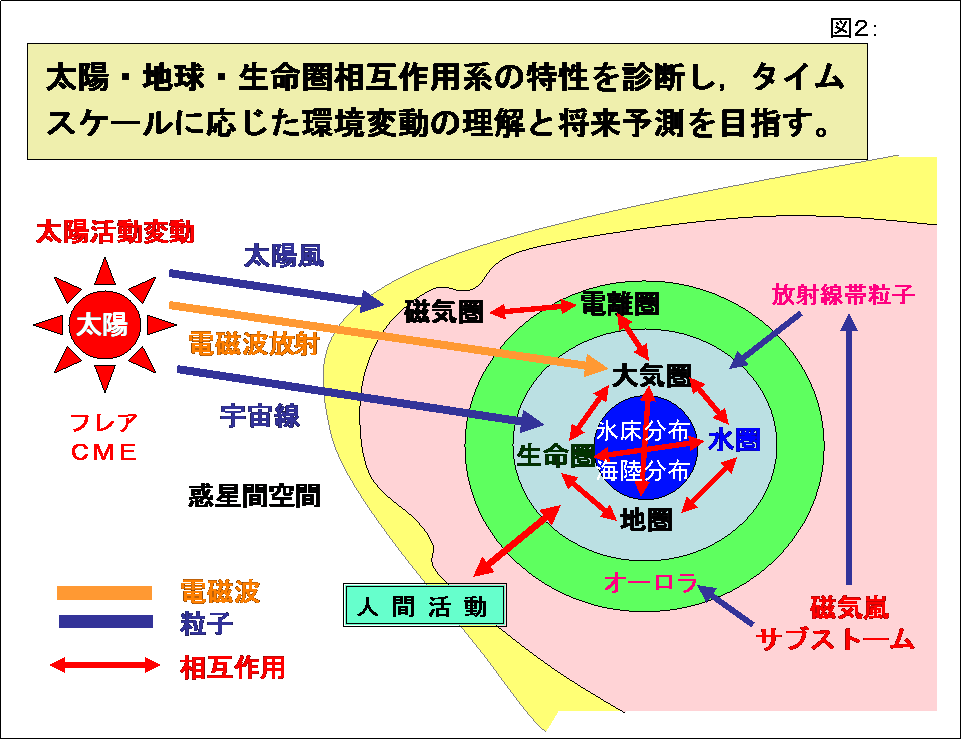
図2:太陽からのエネルギー、プラズマと地球磁気圏、電離圏と下層大気圏の関連を示す模式図
(原図:太陽地球環境研究所 関華奈子氏提供)

図3:エネルギー・水循環過程を通して共存するシベリアのタイガと永久凍土の模式図。
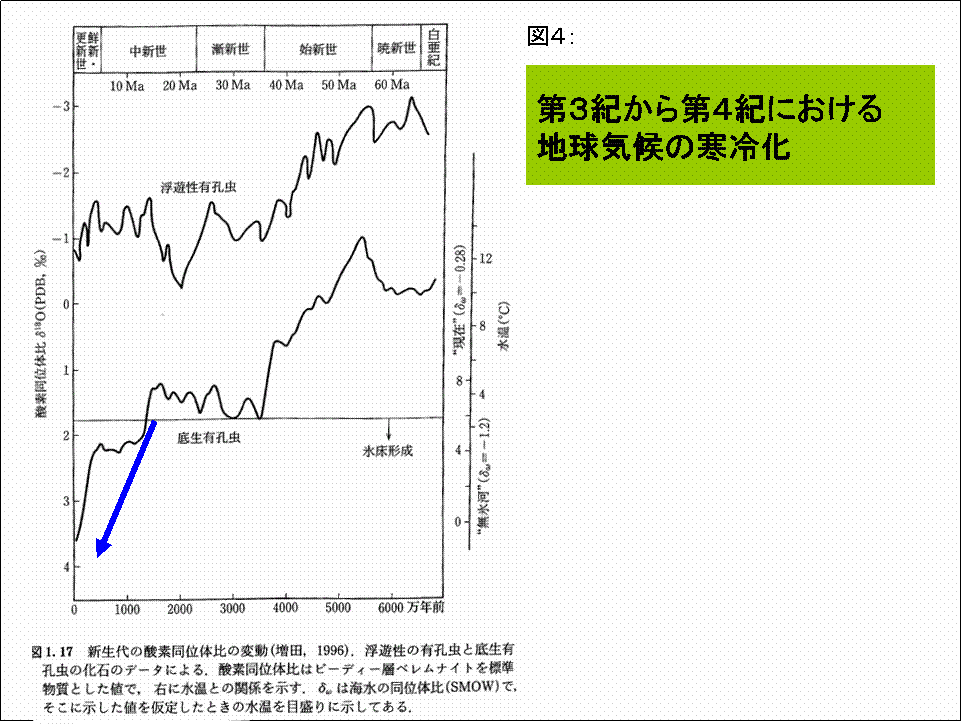
図4:白亜紀から新生代にいたる地球気候の寒冷化(安成・岩坂, 1999 より転載)